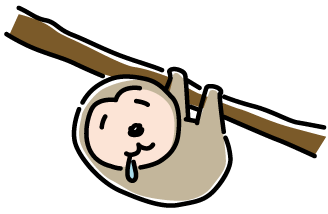専門用語集【五十音順】
い
言い替え
同じ言葉や言い回しが続くと文章が読みにくくなるので、言葉の重複を避けるため、同じような意味の「別の表現」に言い方を替える、ライティングテクニックのひとつ。
●関連記事
⇒すぐ使える三つのテクニック、二重否定/言い替え/倒置法
イメージキャッチ
キャッチコピーの中でも、直接内容を説明するような利便性よりも、印象的な単語や表現を用い、ある特定のイメージを思い描かせたり、興味を掻き立てたりさせる、読み手の印象に残るようなコピー。
●関連記事
⇒「タイトル/イメージキャッチ/見出し」を作るコツは、本文を書いた後に考えよう
き
起承転結(きしょうてんけつ)
文章などの流れを4つのセクションで構成する方法で、4コマまんがなどでの活用がよく知られている。もともとは漢詩の作り方から生まれたとされている。
●関連記事
⇒記事の前後に付け足す「ひとこと」と、思いやりのある表現が親しみを生む
行送り(ぎょうおくり)
行と行の間隔。文字の中心位置から、次の行の文字の中心位置までの距離のこと。似た表現に「行間(ぎょうかん)」がある。
●関連記事
⇒プロが使う行間の黄金比は「全角アキ」が基本。こまめに調整して読みやすく!
行間(ぎょうかん)
行と行の間隔。次の行までの間の空白の距離のこと。似た表現に「行送り(ぎょうおくり)」がある。
●関連記事
⇒プロが使う行間の黄金比は「全角アキ」が基本。こまめに調整して読みやすく!
クライアント
英語でClient。直訳では「依頼人」「顧客」「得意先」などとされ、IT分野やビジネス・取引の現場で使われることが多い。印刷業界では主に印刷物の制作を依頼する企業や組織などを指す。ただし発注の流れが、企業から→広告代理店→デザイン会社→印刷会社と段階を追って発注されていく場合、印刷会社のクライアントはデザイン会社で、デザイン会社のクライアントは広告代理店を指すことがある。大元となる発注企業は「エンドクライアント」などとも呼ばれる。
●関連記事
⇒企画立案からアート制作。原稿やデザイン、入稿まで。広告宣伝物に関わるクリエイターたち
こ
ゴシック体(ごしっくたい)
日本の標準的な書体のひとつ。文字の縦線と横線の太さが均等なのが特徴
●関連記事
⇒プロが選ぶ定番フォントは明朝かゴシック。決め手は視認性
し
スティールカメラマン
ステール(still)は静止画のことで、動画ではなく静止画を専門に撮影するカメラマンのこと。
視認性(しにんせい)
視覚において認識できる度合を言う。見やすさ、読みやすさ、分かりやすさのこと。デザインされたものを見たときに、それが意図した通りに伝わるかどうかは非常に重要で、理解するまでに時間がかかったり、理解されない、また誤解される場合「視認性が悪い(低い)」と言う。
●関連記事
⇒プロが選ぶ定番フォントは明朝かゴシック。決め手は視認性
⇒重なり具合が“心地よい”位置や、見やすさを工夫しよう
写植(しゃしょく)
写真植字を略した言い方。漢字やひらがな、カタカナなど一文字のサンプルを、機械に設置されたカメラを通じて撮影。これを繰り返すことで文章を作り、印画紙に焼き込まれたものを指す。この印画紙を作る機械を写真植字機と呼ぶ。印画紙として出来上がったひと固まりの文字の集まり(文章)は、通常、版下台紙と呼ばれる厚紙の、指定の位置に糊で貼られる。
写植指定(しゃしょくしてい)
文章が焼き込まれた印画紙を作るため、デザイン上、意図した文字の「大きさ・書体・行間・変倍(長体や平体)」になるように指定すること。指定方法は、一般的に文字原稿の余白に、赤インキのボールペンなどで書き加え、写植専門のオペレーターに渡された。
●関連記事
⇒紙の版下って何?[4Hの鉛筆の芯を平たく削れ]
書体(しょたい)
ある一つのデザインとしてまとまりある文字のグループ。同義語としてフォントとも呼ばれる(厳密には書体とは意味が異なる)。
●関連記事
⇒プロが選ぶ定番フォントは「明朝 or ゴシック」。決め手は視認性
せ
全角(ぜんかく)
文字の幅を指す用語のひとつで、ちょうど一文字分の幅を表す。文章中にスペース(空白)を入れる際、一文字分のスペースを入れることを「全角空き(ぜんかくあき)」と呼ぶ。似た言葉に、一文字の半分の幅を指す「半角(はんかく)」があり、半角分のスペースを入れることを「半角空き(はんかくあき」と呼ぶ。修正指示などは「空き」をカタカナで書き「全角アキ」「半角アキ」と記されることが多い。
●関連記事
⇒プロが使う行間の黄金比は「全角アキ」が基本。こまめに調整して読みやすく!
た
体言止め(たいげんどめ)
名詞や代名詞などで語尾を止める文章スタイル。短歌や俳句で使われることが多い。
断ち切り(たちきり)
用紙に印刷後、トンボの位置で用紙を裁断(カット)すること。一般的にトンボの外側は不要部分のため廃棄される。
●関連記事
⇒プロのテクニックを活用し、手持ちプリンターでできるフチなしの印刷物
だ・である調(だ・であるちょう)
「~だ」「~である」で終る文章スタイル。対義語は「です・ます調」。
●関連記事
⇒本文には「です・ます調」を使い、タイトル部分には「だ・である調」が多い
て
です・ます調(です・ますちょう)
「~です」「~ます」で終る文章スタイル。対義語は「だ・である調」。
●関連記事
⇒本文には「です・ます調」を使い、タイトル部分には「だ・である調」が多い
と
倒置法(とうちほう)
文節や語順を逆に書く手法。
●関連記事
⇒すぐ使える三つのテクニック、二重否定/言い替え/倒置法
トリミング
画像を一定のスペース(四角形や楕円形の中)に納まるように、縮小・拡大・回転させるなどして入れること。
トリムマーク
トンボとほぼ同じ意味(正確には異なる部分もある)。インキを印刷するときの目印となる線。また、印刷物を裁断する際の目印にもなる。
この呼び名は主にデザインソフトで使われ、「トリム(trim)」は英語で「切り取る」という意味。
トンボ
トリムマークとほほ同じ。インキを印刷するときの目印となる細い線。また、印刷物を裁断する際の目印にもなる。
厳密には、用紙の四隅にひとつすつ、4か所にある「角トンボ(かどトンボ)」と、用紙の天地左右の中心、4か所にある「センタートンボ」に分かれる。角トンボとセンタートンボの合計8か所を一つのトンボと呼ぶ。
トンボの呼び名は、特にセンタートンボの形が昆虫の「蜻蛉(とんぼ)」に似ていることが由来とも言われている。
●関連記事
⇒プロのテクニックを活用し、手持ちプリンターでできるフチなしの印刷物
に
二重否定(にじゅうひてい)
あえて、言いたいことの逆を言いってから、これを否定する手法。文章では「~ないわけではない」などと書く。
●関連記事
⇒すぐ使える三つのテクニック、二重否定/言い替え/倒置法
ぬ
塗り足し(ぬりたし)
画像などを配置した際、トンボの外側にはみ出てた部分。一般的に仕上がりサイズの端まで写真やイラスト、背景色などを入れる場合、断ち切りの際にズレが出て白地が出ないよう、余裕を持たせてトンボの外側まではみ出させて配置する。
●関連記事
⇒プロのテクニックを活用し、手持ちプリンターでできるフチなしの印刷物
は
パース
奥行きや立体感、空間の広がりを表現するための技法。遠くにあるものほど小さく見え、近くにあるものほど大きく見える法則をグラフィック表現でも再現することで、リアルな三次元的なビジュアルを与えることができる。
いくつかの考え方があり、代表例に「透視図法」がある。これは特定の「消失点」を設けることで、すべての線がその点に収束するように表現する手法で、正面から道路を見た際の「1点消失」。建物を斜めから見たときの「2点消失」。高層ビルを下から見上げた「3点消失」などが代表例。
●関連記事
⇒イラストを描くワンポイント。モノは「傾きと角(カド)」。人物は「骨と関節」
半角(はんかく)
一文字の半分の大きさを表す。文章中にスペース(空白)を入れる際、一文字の半分のスペースを入れることを「半角空き(はんかくあき)」と呼ぶ。似た言葉に「全角(ぜんかく)」があり、一文字分の大きさを表し、一文字のスペースを入れることを「全角アキ(ぜんかくあき)」と呼ぶ。修正指示などは「空き」をカタカナで書き「全角アキ」「半角アキ」と記されることが多い。
版下(はんした)
簡単に言うと印刷の元となるもの。江戸時代は「版木(はんぎ)と呼ばれる木の板に文字や絵などを彫って印刷していて、この版木に彫るための紙の下書きを「版下」と呼んでいたことに由来する。
1950年代に写植が登場し、紙の版下が全盛期となったものの、コンピュータによるDTP(デスクトップパブリッシング)が普及したことでなくなった。現在、まれに版下データと呼ぶことがあるが、印刷用のデジタルデータを指す。
●関連記事
⇒紙の版下って何?[4Hの鉛筆の芯を平たく削れ]
ふ
フォント
ある、ひとつのデザインとしてまとまりのある文字のグループを指す。同義語として書体とも呼ばれる(厳密にはフォントとは意味が異なる)。
●プロが選ぶ定番フォントは明朝かゴシック。決め手は視認性
ほ
ポイント
活字の大きさの単位のひとつ。基準は国によって異なり、日本工業規格では1ポイント=0.3514ミリ。印刷関連は0.3528ミリが慣例。
み
明朝体(みんちょうたい)
日本の標準的な書体のひとつ。横線が細く縦線が太い特徴を持ち、手で書いたような要素を残している。
●関連記事
⇒プロが選ぶ定番フォントは明朝かゴシック。決め手は視認性
れ
レフ板(れふばん)
写真撮影で使われる道具。光を反射させて被写体を照らすための反射板。直接光以外にその光を反射させ、間接光として複数使用することもある。
専門用語集【ABC順】
D/E/F
DTP(Desk top Publishing)
直訳では机上出版や、卓上出版を意味する。パソコン上で印刷物のデータを制作すること。
コンピュータ普及以前は印刷用のデータづくりは主に手作業だったが、PC普及後はこれを実現するためのさまざまな専用ソフトが登場し、一般的にDTPソフトと呼ばれる。
P/Q/R
Pt(point)
日本語の「ポイント」と同じ。Ptは「point」の略称。活字の大きさを示す「ポイント」の単位。基準は国によって異なり、日本工業規格では1ポイント=0.3514ミリ。印刷関連は0.3528ミリが慣例。